ユーザー理解を深めていくと文化人類学的な視点にたどり着く
日常のコミュニケーションや表現のなかにも理解が困難な壁がありますが、文化人類学的なアプローチを考えることで解像度が上がります。非常に重要な視点だと感じ、今回インタビューを依頼しました。
小川さん:ありがとうございます。正直UXと言われても何のお話をすればいいか悩んでしまったのですが、そういうことであればお話しできるかもしれません。
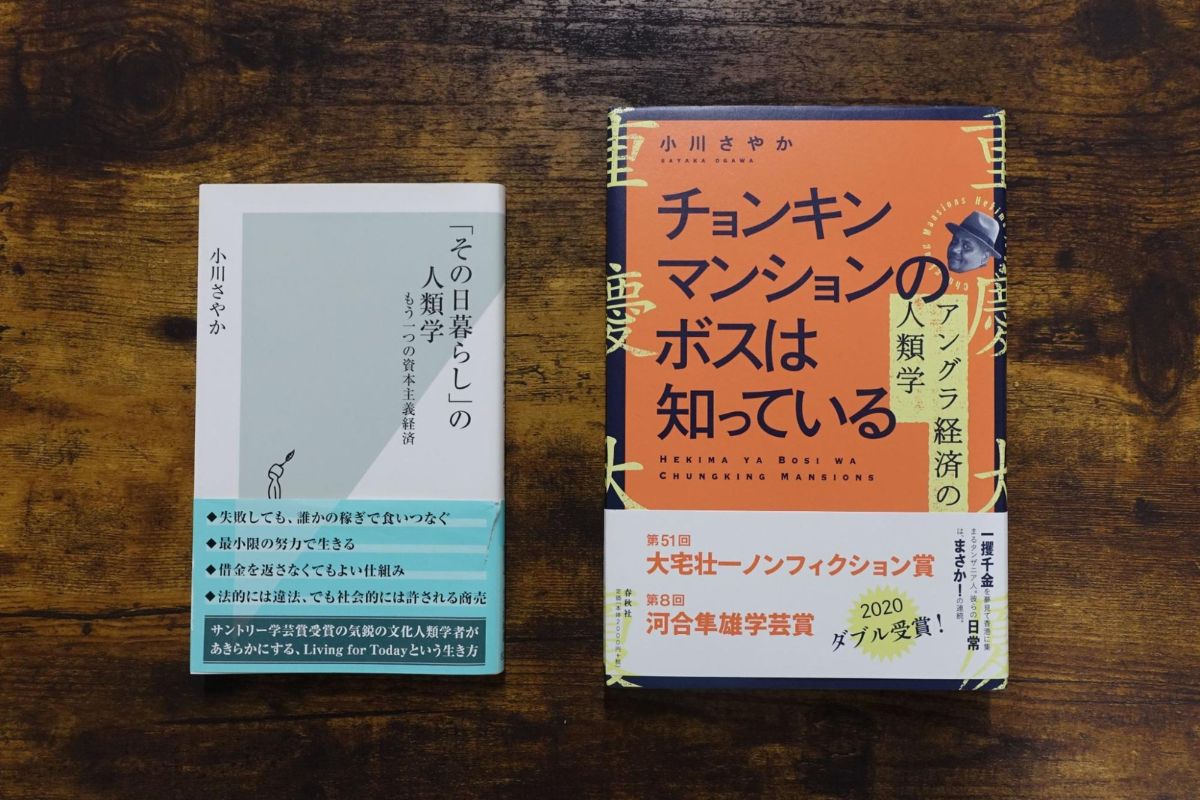
(以下、お写真は全て小川さん提供)
研究されてきたタンザニア商人の商習慣を振り返りながら一緒に考えていけたらと思うのですが、少しご紹介いただけますか。
小川さん:わかりました。まずデジタルではない話から始めたいのですが、私はタンザニアに調査に行くときに、よく日本製の海外旅行向け製品を持っていきます。手のひらサイズの電気ポットとか、懐中電灯がついているラジオとか、お土産に受けが良さそうじゃないですか。ところがタンザニアの人たちは、軽量化・個人化された商品にはあまり興味を持たないんです。塵や埃が舞うタンザニアでは高機能な製品ほどすぐに壊れてしまうということもありますが、何より、個人化されていると「未来」を考えた時に使いにくいからです。
小川さん:タンザニアではほとんどの家庭が大家族です。だから大きい製品の方が転売しやすいし、田舎の親族にプレゼントだってできます。傘にしても、私は折り畳み傘を持ち歩きますが、タンザニア人からすると、誰かを入れてあげたいと思っても入らない折り畳み傘は使いにくいんです。
使っている時にシェアできて、使ったあとも誰かに売ったり贈与したりできる製品をタンザニア人は好みます。物品を購入する時に、商品の「未来」を想像しているって、面白いですよね。
小川さん:モノに自分の魂が宿ることを前提に生きているからです。マルセル・モースという有名な研究者が書いた『贈与論』という本の中にマオリの人たちが描写されているのですが、そこにも「贈り物には贈り主の魂や人格が宿っていて、贈り物が返ってくるのは、物に宿った贈り主の魂が元の持ち主のところに戻りたいと思うからだ」と書かれています。
タンザニアの人たちはよく贈り物をするのですが、相手がピンチな時や困っている時に贈り物をすると、受け取った相手は自分の心と共に生きていくと考えるんです。
実際に聞いた話ですが、ある木材商人が商売に失敗して木材問屋に掛け売りを頼みました。その問屋の女性には亡くなった甥がいて、彼は商売こそ下手だったものの手先が器用で、生前は家具職人として成功していたそうです。
問屋の女性は木材商人に「あなたは甥に似ているから職人に向いている」と言って、甥の遺品であるカンナなどの職人道具をあげました。その後商人は独立した家具職人の工房を開いたのですが、「道具の手入れをしていると、いつも木材問屋の女性を思い出す」「いまはまだ余裕がないけど、いつか木材問屋の女性に良い家具をプレゼントするのが夢だ」と話していました。
こんなふうに、モノには元の持ち主の想いが宿っていて、今の持ち主の人生に働きかけることもあります。元の持ち主の想いがあるから自分も真面目にならなきゃとか、頑張らなきゃとか、いつも笑顔でいなきゃとか思わされるんです。贈り物は時々重いし、毒にもなります。魂があまりにも重すぎるとそれが縛りになって、時に自分らしいことができなくなるといった面すらあります。オカルトチックな話ですが、私たちもなんとなく理解できますよね。

小川さん:タンザニア人にとってモノは誰かに自分自身の影響を与えられる存在なんです。ピンチの時にその人が欲しいモノをあげたとしたら、それは自分の手を離れても、受け取った人の人生や生き方に作用する、と考えられています。
日本に住む私たちは、モノに想いが宿るというと形見やお守りや手編みのマフラーぐらいしか思いつきませんが「誰かと誰かを繋ぐモノ」は確かに存在します。売る人や贈る人側の想いが上手に乗せられて誰かの人生に作用するような。そう考えると、所有し続けるのではなく、意図的に物を手放したほうが人生が豊かになっていくという考えにも合理性があります。
小川さん:していますね。でも私たちが考えるシェアの概念とは少し違う形かもしれません。タンザニアでは、14歳以上の労働人口のうち銀行預金を保有しているのが20%強ぐらい。それは成功する商人がいないわけではなくて、成功した商人たちが、違うビジネスにどんどん投資しているからなんです。彼らは投資する時にモノを買います。例えば中古自動車を1台買って、それを仕事が無い若者に貸してちょっとずつ返してもらう。そして元が取れたら、その中古自動車はその人や他の人にあげてしまう。そうやって自分の仕事の機会や再起を図るチャンスに繋がるモノを贈り、受け取るんです。
500人とか1,000人とかをそうやって助けておくと、中には成功する人が数人はいて、自分には貯金が無くてもその時々で実りのある商売をしている人たちに便乗していけば食いっぱぐれがない、みたいな感覚で老後まで人生を送るんです。
小川さん:日本人の私たちからすると、シェアといえば、環境を保護するために資源を有効活用しよう、というような感覚ですが、彼らを見つめているともっと自然に……自分自身が柔軟に楽しく過ごすために持っているモノをシェアしていく、というような仕組みがあったらいいな、と思わされますね。
タンザニアでのTikTokの使われ方
小川さん:前回タンザニアに行った時は、InstagramやTikTokを使ったマーケティング戦略について調査しました。彼らの広告戦略や商売の仕方は、ぱっと見た印象では日本のYouTuberに似ているのですが、実は全然違います。
彼らの「お店」は、今、SNSと密接に絡み合っています。InstagramやFacebookに商品の画像や動画をあげたりして、そこに希望販売価格と連絡先を書いておく。あとはWhatsAppというチャットアプリ経由で個別に売買交渉して、購入が決まったらGPSを利用したデリバリーアプリを使って配達をします。電化製品でも衣料品でもなんでもあって、購入してから1時間後には手に入ることも。
もちろんSNS投稿は頻繁に行われるんですが、商品とはまったく関係がない投稿も多いんです。下着を売っている商人が、下着が並んでいる店の棚の前でラップダンスをする動画とか、自分の結婚式で流れる家族写真みたいな画像とか、商品が売れなくて奥さんに怒られているコントみたいな動画とか、そんな投稿もかなりたくさんあるんです。
小川さん:もともとタンザニアのSNS経由の商売の世界って、有象無象の商人たちが売っているから、アカウントを消して飛ばれちゃって、商品が届かない時もあるんです。タンザニアには住所が無いので飛ばれたら居場所は分からない。だからタンザニア人は、商品はできるだけ知り合いや、知り合いの知り合いから買います。SNSは欲しい商品を探す場ではなく、商品を持っていそうな知り合いを探す場なんですね。
ある時、中国から輸入した髪染めを宣伝する動画を作成している現場にお邪魔したのですが、動画自体は単純で、髪染めの方法やモデルの男性の頭が白髪から黒髪になるBefore/Afterを見せる動画でした。ただ、モデルの男性がふつうのおじさんで、よれよれのシャツを着ていたんです。「せめてアイロンをかけたらいいのに」と言ったら、「これがいいんだ」と言う。そのおじさんは商人たちにとって仲買人みたいな人で、たくさんのネットワークを持っていて、商人たちを助けてきた有名人。そんな顔の広い彼がみすぼらしい格好で動画に映っていれば、商人仲間が「あいつがピンチだ、助けなきゃ」と思って動画をリツイートしてくれるはずだ、というのが彼の戦略だったんです(笑)。
タンザニア商人たちの関係は恩や贈与で回っていて、恩人や、恩人の恩人が困っていたら自分たちも助けなければ、という流れで商品が売れます。面白い話ですよね。

右:SNSを通じた販売
小川さん:そうだと思います。私たちが誰かから物を買う時は、詐欺じゃないかとか、きちんと届くかということに気を配りますよね。タンザニアの人たちは、今この人が困っているから買おうかなとか、ちょっとこの人は面白そうだから繋がりたいなとか、そんな理由で物を買います。売り手が日常的にどんなことをしているのか、どんなふうに人々を助けてきたかということが実を結ぶんですね。そういう買い方をすると、モノに込められた心が増長されて、いつか何かが起こると信じているんです。

小川さん:タンザニア商人に評価システムについて話をすると、意味がわからないと言われます。商人の配達が遅かったとか、画像と違う商品が来たとか、他の商品より高く売られたとか思ったとしても、彼らは「悪質な業者です」とかいう評価はしません。SNSには商人の日々の生々しい姿が一緒にくっついていて、浮き沈みがある人間の世界というのを商品とセットにして売っているためです。
でもこれはTwitterなどと同じで、なんの強制もなければ、性善説に基づいているわけでもありません。基本9割くらいスルーなのですが、全部スルーしていたら自分のフォロワーもゼロですよね。それに対して、ちょっと気分が乗ったら「いいね」をするとか、「友達が今ピンチだ。この時に反応すれば絶対にこの人は自分のフォロワーになるな」と考えてアクションするとか、作戦をもってSNSを使えば自分のフォロワーが増えるわけじゃないですか。
自分にだって困っていない状況と困っている状況はあります。困っていない状況の時にちょっと騙されたとしても「この人はわざと騙されてくれたんだ」と匂わせておけば、自分が困った時にその騙した相手に「この間、俺、騙されてあげたよね」とさりげなく主張して助けてもらう。保険みたいな感じですね。
人生の浮き沈みは相手にも自分にもある。自分がちょっと調子がいい時に投資や賭け事をしておいて、沈んでいる時に挽回するというタンザニア商人のビジネスは、かなり戦略的というか実利主義的だと思っています。
小川さん:助けを求めに行っても相手に余裕がないと分かったら「ごめん、挨拶に寄っただけだから」と帰ることもあります。ただ、繋がっている相手が100人いたら、その時にちょうど商売がうまくいっている人は、絶対に何人かいるはず、という考え方なんです。
感情をベースにしたビジネス
小川さん:もちろん触れ合っています。グローバル資本主義の末端にタンザニアも組み込まれていますから。システマチックな世界を引き受けざるを得なくて、競争しながら成功を目指して頑張っている一面も持っています。ただ、自分が行き詰った時に、「お前の自己責任だ」とか「しくじったやつらは細々と寂しく生きればいい」とか言われる世界になったら悲しいですよね。だから、資本主義経済の中で頑張って生きていくために、しくじる可能性を見越して、心に余裕がある時に落ちた時のリスクヘッジみたいなのをかけておくんです。
小川さん:タンザニアの場合は顔が見える世界ですが、顔が見えるか否かに関わらず恩送りのしくみはありますよね。「カルマキッチン」のような取り組みがそれにあたります。「カルマキッチン」というのは、自分の食事が自分の前に来た人によって支払われているシステムです。自分はただで食べられて、後から来る人たちのためにお金を置いていきます。余裕が無い時だったら置いていかなくてもいいし、「今日は誕生日を祝ってもらってすごい幸せだったからおすそ分けをしたい」と思ったらたくさん置いていってもいい。訪れる人たちの運によって回っている食堂です。
小川さん:例えば、記憶を持ったお金ができたら面白いと思いませんか。お金は人から人へ所有権が移るものですが、そこで大事なのは、誰から誰に移ったかということよりむしろ、移る時にどういう出来事があったかではないでしょうか。
例えば紛争の和解などの重大イベントでは、たくさんお金を支払えばいいわけではないですよね。大切な人が亡くなった時に、誰しも「お金の問題じゃない」「私の大切な人はお金を積まれたって戻らない」と思いますから。むしろ、過去に同じような出来事があって和解した時に支払われたお金かどうか、つまりその記憶が基準になります。受け取ったお金が、その人や集団がかつて自分の大事な人を失った時に泣く泣く受け取ったお金だとしたら、その重みは一緒かもしれない。感情的にすごく理解できませんか。
お金に色が付いていて、お金同士が混ざり合うとどんどんレアな色になっていくとしたらどうでしょう。悲しい色と悲しい色をかけていくと更にどす黒い色になっていく、でもいいのですが。相手が出したお金の色を見て、「この色のお金だったら受け取ってもいいかな」という気分になれるとしたら。
もしくは自分がピンチの時に誰かを助けて、その時に貰った特殊色の貨幣を、交換を通じてどんどん特殊にしていく。トークンだったらできると思うのですが。そのトークンは貨幣価値にすると500円くらいしかなくて、でも「こんな特殊な色の貨幣はないだろう!」というレアなもの。それを取っておいて、自分が超ピンチのときに「ちょっとこれ見て!」と切り札みたいに出せるようになると、経済システムも、感情的な世界もどちらも回るんじゃないかと思います。
貨幣そのものは指標なので、今お話したことには何の裏付けもないのですが、人類学をやっていると「例えば」という妄想はどんどん広がります。ある礼儀やシステムに出会うと、「これをデジタル世界に反映させるとしたら」とか、「この論理だけを吸い上げてやるとしたらどうなるだろう」などと考えてしまいます。その面白さを実現しているシステムの、理論だけをこちらの世界に組み込んで何かができないかな、って。
文化人類学の視点で世の中を眺める
でも、ユーザーを正しく理解するためには一度全ての枠を外して、ありのままの姿を見にいくことも大事なのかなと考えさせられました。
小川さん:文化人類学の調査法の一つに、「参与観察」があります。いかに奇異に見える習慣や文化に出会っても、自分たちの常識をわきにおいて見つめてみる。私たち文化人類学者は、タンザニアやアマゾン、中国の奥地など世界各地に入り込んで、他の人々のまなざしや世界との関わり方を体感して、そこから翻って自分たちが生きている世界を見直すという作業をしています。そうした考え方はユーザー視点の理解に役立つかもしれません。
タンザニアに行くと、最初は「タンザニア人はなぜこんなふうに知らない人たちと信用取引をするんだろう」と驚くのですが、調べるにつれて、「これが彼らの信頼の形なんだ」と分かってきます。そうすると、自分たちはいつの間にか消費経済にどっぷり浸かって、減点主義で生きているけれど、もう少し柔軟に考えた方が楽しいんじゃないか、と思い直してくるんです。そして日本に帰ってきて、「ここではそんなに簡単にはできないよね」と思うと、今度はなぜ日本でできないかをいろいろ考え始めます。私たちが「もうこのシステム以外では回らないだろう」と思っている常識の外側でなんとか回っている人たちを見ると、「もしかしたら、このシステムじゃなくても回るのかも」と気がつくんです。
私たちとは違う世界でちゃんと生きて回っている人たちの発想を、私たちが普通だと思ってやっている一個一個にぶちこんでみる。「ちょっと日本では無理」ということもあるでしょうが、新しい視点が生まれてくる場合もあります。こうした考え方に注目した企業が、文化人類学者を雇うというケースも少しずつ生まれているようです。
小川さん:『ANTHRO VISION』(ジリアン・テット著, 2022年)がいいのではないでしょうか。具体的な手法やいろいろな事例が紹介されていて、私は日本で購入できる書籍の中ではこれが一番わかり易いと思っています。
小川さん:比嘉夏子さんはどうでしょうか。人類学者の視点を企業にインストールすることを目指している方です。メッシュワークという会社を立ち上げて、中国などの海外でフィールドワークをしたり、そこの人々がアンケートや質問に書かないけれど日常的に行っている行動などを観察したりしながら、その土地に合った製品やその土地の人々が楽しいと考える製品を作っていくというプロセスを企業の人と一緒にやっています。従来のビジネスでは身につかなかった新しい発想、今までと異なる視点をどんなふうにしたら獲得できるか、人類学的な発想や思考法を組織向けに画策したり、セミナーで教えたりされています。京都大学でご一緒してから、ずっと仲良くしている方です。
今回のまとめ
文化人類学とUX。藤井さんからこのキーワードを聞いた時はいまいちピンときませんでしたが、UXの基本である「ユーザー視点の理解」のプロセスにおいて、文化人類学的な考え方が重要なことを実感しました。
・タンザニアの人々にとって商品は「誰かと誰かを繋ぐモノ」
・感情をベースにしたビジネスが成立する場では、マーケティングも変わる
・ありのままの姿を見つめる「参与観察」はUXの現場でも使える手法かもしれない
人々の期待や価値を感じるポイントが、顧客やユーザーの文化的背景によって異なるのは当たり前のこと。しかし単一民族である私たちは、そうした背景の違いに目を向けることが少ないのかもしれません。隣の人が自分と同じ価値観を持っているという前提を外し、文化人類学における観察手法を参考に世の中を見つめ直してみると、新たな発見があるかもしれません。

小川さやか(おがわ・さやか)
立命館大学先端総合学術研究科 教授。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科一貫制博士課程指導認定退学。博士(地域研究)。国立民族学博物館機関研究員、同助教、立命館大学先端総合学術研究科准教授を経て現職。主な著書に『都市を生きぬくための狡知—タンザニアの零細商人マチンガの民族誌』(2011年、世界思想社、第33回サントリー学芸賞受賞)、『チョンキンマンションのボスは知っている—アングラ経済の人類学』(2019年、春秋社、第8回河合隼雄学芸賞・第51回大宅壮一ノンフィクション賞受賞)、『「その日暮らし」の人類学』(2016年、光文社新書)など。1978年生まれ。




