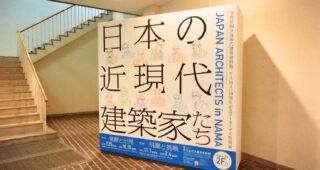インハウスデザイナーが集まる場をつくる
領域・業界を限定せず、幅広く多様なデザイナーが集まる場をつくることができないか? 本イベント「Neuron」は、そんな問いからはじまった。そして着目したのが、企業に所属するインハウスデザイナーの存在だ。
あらゆる事業が多角化していく現代社会において、インハウスデザイナーが活躍するフィールドはグラフィックやプロダクト開発にとどまらず、空間設計、WebやアプリケーションのUX/UI、サービスデザインに至るまで現在進行形で拡張し続けている。デザインメソッドを活かした既存の製品やサービスに関する課題解決に加え、未来の「コトづくり」に取り組んでいるケースも多数ある。
「Neuron」は、そんなインハウスデザイナーを中心としたネットワーキングと創発の場としてスタートした。
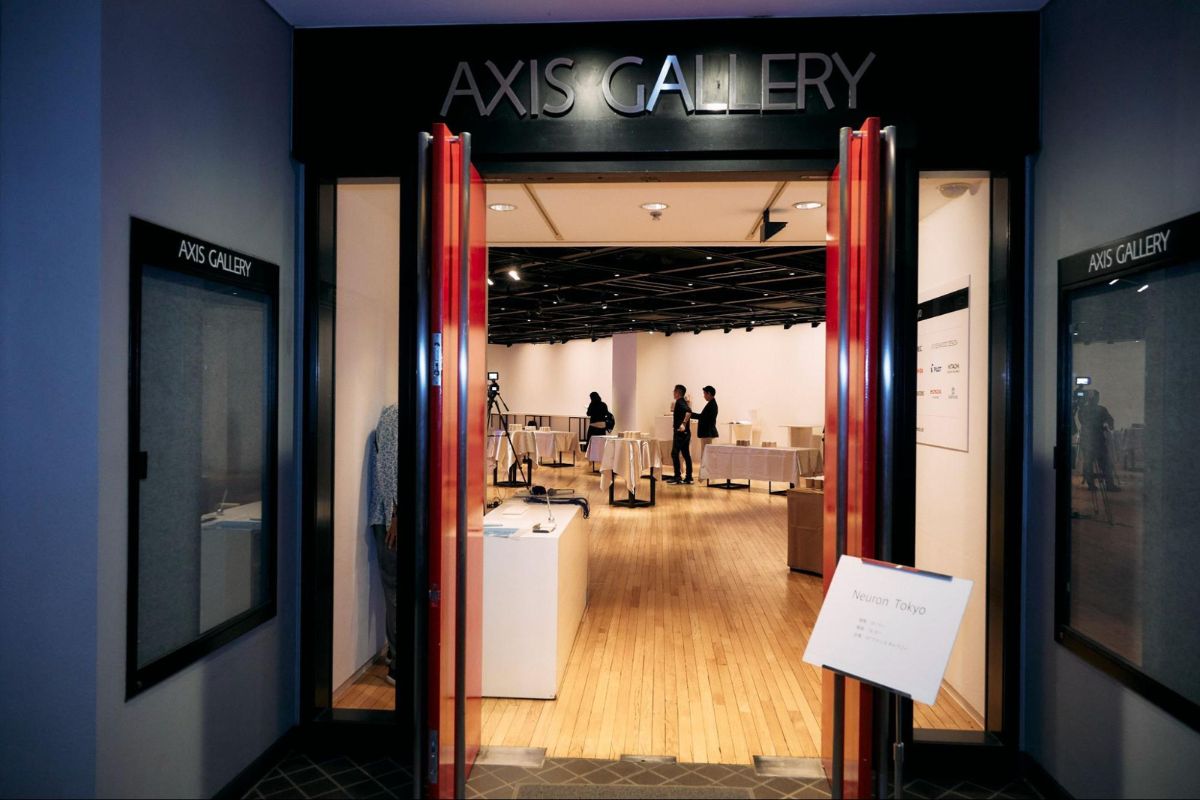

課題を乗り切るキーワードは「パラドックス思考」
第1回「Neuron Tokyo」のテーマは「デザインの力で“無理ゲー”課題を乗り越える」。インハウスデザイナーは日々の業務の中で、往々にしてさまざまな矛盾(パラドックス)をはらんだやこしい問題に直面しているものだ。
「自社の利益を最大限に追求しながら、社会的責任も果たさなければ」
「プロダクトの機能を増やしたいが、さらに使いやすくしてコストも下げたい」
「自社らしさを失わず、かつ新規性に富んだデザインを生み出したい」
そんな数々の“無理ゲー”課題の乗りこなし方についてイベント冒頭に語ってくれたのはゲストスピーカーの安斎勇樹さん(株式会社MIMIGURI 代表取締役 Co-CEO)。
「長年、無理ゲーについて探究してきた」という安斎さんは、自身が関わったプロジェクトを挙げ、「問いの立て方」を変えることで新たな視点を得て、クライアントの課題を解決した事例を提示してくれた。一方で、良い問いを立てることは難しく、それを邪魔してしまう人間の思考があるとも話す。それが、2023年3月に刊行された安斎さんの著書のタイトルにもなっている「パラドックス思考」だ。

「人間は誰しも『挑戦したい。でも失敗はしたくない』というように、相反する感情を持っているものです。しかし多くの場合、その片側の感情をなかったことにしてしまう。そうすると、課題はより解決しづらくなってしまうのです。
矛盾した感情も素直に受け止めて、どうしたら両立できるか? と考えることが、無理ゲー課題を乗りこなす一つのヒントになるのではないでしょうか」(安斎さん)

それぞれが挑んでいる”無理ゲー”とは?
ゲストトーク終了後、9社のインハウスデザイナーが、それぞれが乗り越えた、もしくは現在進行形で直面している“無理ゲー”といえる難題についてプレゼンテーションを行った。
以下、その内容をダイジェストで紹介する。
NEC(日本電気株式会社)
大谷京香さん(コーポレートデザイン部)
新入社員として入社後、技術広報からはじまり、新規事業のビジョンづくり、株主総会や記者発表などの担当を経て、CEOのコミュニケーションデザイン担当チームとして活動している自身のキャリアを紹介。毎回「そんなのやったことない!」と悩みながらも、与えられた課題を一つひとつクリアしていくことが、将来的には自分自身の強みになると納得して向き合えるようになったそう。

富士フイルム株式会社
田口雄さん/今村響さん/小林寛さん(デザインセンター)
自社ブランドの新たな製品を開発するにあたり、ブランドの「らしさ」と、プロダクトとしての「新規性」を両立させた成功事例を発表。客観的な市場分析の視点に加え、プロダクト・グラフィック・UIのデザイナーがタッグを組んで「愛があれば乗り越えられる」と、開発チームが大切にしていたマインド部分を繰り返し強調した印象的なプレゼンテーションであった。


株式会社東芝
本間多恵さん(CPS×デザイン部)
あるとき、デザインチームに突然降って湧いた重大ミッション「震災被害を受けた街の復興プランを作って欲しい」。時間もなく要件も不透明な状況で「わからないからできない」ではなく、「わからないなら聞けばいい」と、完成されたアイデアではなくクライアントの要望や想いを引き出すために必要なコミュニケーションのツールをデザインした事例を紹介。

株式会社日立製作所
吉治季恵さん/園田幸子さん(デザインセンタ、UXデザイン部)
電車の座席など、公共サービスに関わるデザインの難しさや、自分たちが日々試行錯誤しているプロセスなどを紹介。デザイナーが最終的な意思決定をするのが難しい領域ではあるが、可能な限り利用者や対象地域とのコミュニケーションを図りながら、試行錯誤を繰り返していくことが重要だと感じているという。

シチズン時計株式会社
三村章太さん(商品開発本部 デザイン部)
現在進行形で課題にぶつかってしまっている社内プロジェクトを紹介。これまでいくつものハードルをクリアしてきたものの、思わぬところで暗礁に乗り上げてしまった。この“無理ゲー”を何とか乗り越えるべく、これからもチャレンジしていくつもりだという。会場に向かって「どうすればいいと思いますか?」と問いかける場面も。

株式会社パイロットコーポレーション
岩﨑由紀子さん/神戸萌さん
(グローバルマーケティング本部 グローバル企画部 デザイン室)
認知度、市場シェアなどで他社に圧倒的な差をつけられていた製品の開発・販売戦略についての成功事例を発表。「自社製品はユーザーにとってどんな存在か?」と問い直し、ブランドコンセプトとメインターゲットを再確認したうえで、徹底してそれらに忠実な企画を練りあげることで成果を挙げた。

株式会社ブリヂストン
齋藤圭吾さん/菊地学さん(プロダクトデザイン室)
「デザイン性が大事」「機能性が第一」と、それぞれ異なる価値観を持っていたという2人のプロダクトデザイナーが登壇。それぞれの思考を尊重しつつ、それをどのようにすり合わせ、どうすれば実用性と見た目を両立したプロダクトがデザインできるか、協力しながら模索を続けている。

株式会社JVCケンウッド・デザイン
望月琴未さん(カスタマーエクスペリエンススタジオ)
事業コンセプトもターゲットも何も決まっていない状態の新規プロジェクトに、デザイナーとしてアサインされた経験を発表。「何をデザインすればいいかわからない」状態で、自分にできることを模索。会議で出たアイデアをグラフィカルに可視化したり、プロジェクト自体のロゴを作成したり、デザイナーだからこその存在価値を発揮した。

本田技研工業株式会社
澤井大輔さん(デザインセンター、アドバンスデザイン室)
事業ではなく、趣味でBBQ大会に取り組んだ経験を発表。ユニークな語り口に最初は会場からも笑いが起こっていたが、勝つための戦略策定、コンセプト設計、生成AIの効果的な活用など、確実に成果をつかみとるデザイン思考とそのプロセスの見事さに、プレゼン終盤には感嘆の声があちこちから漏れていた。

新たなアイデアが生まれる場として全国展開予定
本イベントは今回のように、ゲストによるトーク、企業の若手デザイナーによるプレゼンテーション、懇親会で構成し、「Neuron Tokyo」を皮切りとして、今後は日本各地で定期開催していく予定だ。
「Neuron」という名の通り、ヒトの神経細胞のように、個々の想いや新たな情報から刺激を受けることで、今までにないアイデアやプロジェクトにつながっていく——そんなきっかけとなる場を目指している。